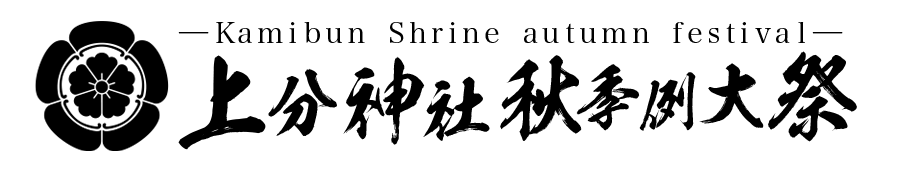祇園祭は、京都の夏を彩る日本を代表する祭りの一つです。毎年7月1日から31日にかけて行われるこの祭りは、八坂神社の氏子区域を中心に開催され、多くの観光客や地元民が楽しみにしています。本記事では、祇園祭の歴史や見どころ、山鉾について詳しくご紹介します。
祇園祭とは
祇園祭は、八坂神社の祭礼として千年以上の歴史を持つ伝統行事です。疫病退散を願い、古くから京都市民に愛されてきました。7月を通じて行われる祭りの中で、山鉾巡行や宵山といった行事が特に有名で、祭り期間中は京都の街全体が賑わいを見せます。
歴史
祇園祭の起源は869年、貞観11年にさかのぼります。当時の疫病流行を鎮めるため、御霊会(ごりょうえ)という儀式が行われたことが始まりです。この時、神輿が京都の街を巡行し、人々が災厄の沈静を祈ったとされています。その後、山鉾巡行が祭りに加わり、現在の形に発展しました。
日程
祇園祭は1か月にわたって行われますが、主要な日程を以下の通りです。
・7月1日~5日: 吉符入り(祭りの準備開始)
・7月10日~12日: 山鉾建て(山鉾の組み立て)
・7月14日~16日: 前祭の宵山(夜のライトアップと賑わい)
・7月17日: 前祭の山鉾巡行(23基の山鉾が巡行)
・7月24日: 後祭の山鉾巡行(10基の山鉾が巡行)と還幸祭(神輿が八坂神社に戻る)
・7月31日: 疫神社夏越祭(祭りの締めくくり)

祇園祭の氏神 八坂神社について
八坂神社は、京都市東山区に位置する神社で、素戔嗚尊(スサノオノミコト)を主祭神としています。疫病退散や厄除けのご利益があるとされ、祇園祭の中心的存在です。神社は観光地としても有名で、年間を通して多くの参拝者が訪れます。
祭りの見どころ
祇園祭の見どころは何といっても山鉾巡行と宵山です。
・宵山では山鉾が提灯で美しく飾られ、歩行者天国となった通りを散策しながら祭りの雰囲気を楽しめます。
・山鉾巡行では、豪華絢爛な山鉾が京都の街を巡る様子を間近で見ることができます。

山鉾の種類
祇園祭には、前祭と後祭で異なる山鉾が登場します。以下はその代表的なものです。
前祭(7月17日)
・長刀鉾(なぎなたほこ)
・函谷鉾(かんこほこ)
・鶏鉾(にわとりほこ)
・月鉾(つきほこ)
・放下鉾(ほうかほこ)
・芦刈山(あしかりやま)
・蟷螂山(とうろうやま)
・綾傘鉾(あやがさほこ)
・岩戸山(いわとやま)
・船鉾(ふなほこ) など23基
後祭(7月24日)
・北観音山(きたかんのんやま)
・南観音山(みなみかんのんやま)
・鯉山(こいやま)
・浄妙山(じょうみょうやま)
・橋弁慶山(はしべんけいやま)
・大船鉾(おおふなほこ)など10基

祇園祭の楽しみ方
祇園祭を楽しむには、以下のポイントを押さえるとよいでしょう。
宵山で山鉾を堪能: 提灯が灯る夜の山鉾は美しく、祭り気分を盛り上げます。
ちまきを購入: 厄除けのお守りとして販売されるちまきは人気です。
屋台を楽しむ: 宵山期間中は多くの屋台が出店し、グルメやゲームを楽しめます。
山鉾巡行を見る場所を確保: 巡行当日は早めに場所を確保すると快適に観覧できます。
まとめ
祇園祭は、千年を超える歴史と伝統を持つ日本を代表する祭りの一つです。八坂神社のご加護の下、豪華な山鉾や賑やかな宵山が訪れる人々を魅了します。今年の祇園祭には、ぜひ訪れてその魅力を体感してみてください。
参照元:
祇園祭に関する歴史資料
八坂神社公式サイト
京都市観光協会の祇園祭情報