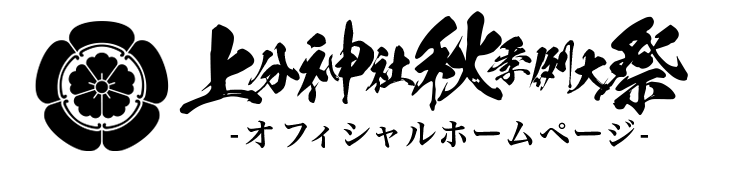どうして祭りをするの?太鼓台ってなんのため?
秋になると、あちこちの町でにぎやかな祭りの音が聞こえてきますね。上分町でも、毎年10月に太鼓の音が響きわたり、おみこしや太鼓台が町を練り歩きます。でも、みなさんは「なんのために秋祭りをするのか」考えたことはありますか?

秋祭りは“ありがとう”を伝える日
秋祭りのはじまりは、神さまに「たくさんのお米や野菜が実りました。ありがとうございます」と感謝を伝えることから始まりました。町の人たちは、のぼりやちょうちんをかかげて、神さまの乗った「おみこし」をかつぎ、田んぼや畑のそばを歩いて、実りの様子を見てもらっていたのです。
でも、祭りの意味は町によってちょっとずつちがいます。たとえば、海の近くの町では「魚がたくさんとれますように」と願う「大漁祈願」が込められています。私たちの住む上分町のように山にかこまれた場所では、「五穀豊穣(ごこくほうじょう)」といって、お米や野菜などが元気に育つことへの感謝が中心です。

太鼓台ってなんであるの?
太鼓台は、今でこそ秋祭りの主役のような存在ですが、いつから使われるようになったのかは、はっきりわかっていません。
一つの考えでは、京都の「祇園祭」に出てくる「かき山(山車)」がもとになったとも言われています。戦国時代のころ、大阪の商人がはでな山車を作らせたことがきっかけだったという説もあります。
江戸時代には、ふとんをかさねたような形の太鼓台が登場し、見た目もにぎやかになっていきました。人々の暮らしが豊かになる中で、祭りもどんどんはなやかになっていったのです。また、船がたくさん行き来していた時代、京都などの文化が海をこえて地方に伝わりました。その流れで、太鼓台も瀬戸内の町に広がったと考えられています。ほかにも、「村上水軍がもとになった」「大阪城の石を運んでいたときに生まれた」などいろいろな説がありますが、本当のことはまだ分かっていません。

太鼓台のやくわりとは?
太鼓台の役目は、町によってちがいますが、ふつうは次の2つの意味があります。
1.町の中をまわって悪いものをはらう「厄払い」
太鼓台が町の中をまわるのは、悪いことや病気を追いはらって、町をきれいにするためでもあります。元気な声を出しながら、みんなの気持ちをひとつにして歩くことで、神さまが通るための大事な道をととのえるのです。昔から、太鼓台にある「りゅう」や「ふさ」のかざりには、雨をふらせてお米を育てる力をよぶ意味もあったそうです。音を鳴らすことで、空気や町のけがれをはらい、おいのりの気もちもこめられています。
2.神さまの乗ったおみこしといっしょに歩いて、お供をする
神さまがのっている「おみこし」が町を歩くとき、太鼓台はその後ろを進んだり、いっしょに歩いたりします。これは「神さまのおとも」をする大事なおしごとで、神さまの行列をもっとすてきに見せるためのやくめもあります。また、神さまが少し休む場所(御旅所といいます)では、太鼓台がその前ではなやかな動きや音を見せることで、神さまに楽しんでもらうという意味もあるんですよ。
太鼓台は、ただにぎやかに音を鳴らしているだけではなく、大事な役目をもっているのです。
まとめ

秋祭りは、神さまに感謝し、町を清める大切な行事です。太鼓台も、おどろくほど長い歴史や意味を持っています。毎年見ている祭りの風景には、先祖たちの思いと地域の文化がたくさんつまっているのです。今年の秋祭りも、ただ楽しむだけでなく、「なぜやっているのかな?」と考えながら見てみると、きっといつもとちがう発見があるはずです。
column2025